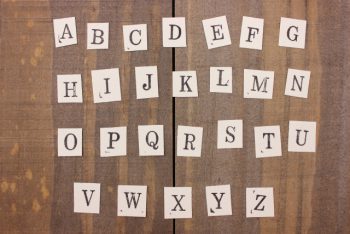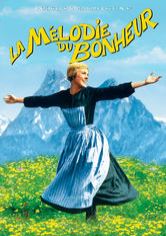前回、前々回とたまたま英語に関する話につながってしまったので、前からずーっと感じていることを書いてみようと思う。
今はここフランスに住んでいるわけなのだけど、フランス人といえばフランス語に誇りを持っていて英語を話してくれない、というイメージを持っている人も未だにいるかも。でも、それはもはや昔の話で、今の若いフランス人はけっこう英語が上手。街なかで外国人観光客に英語で何か尋ねられて英語で返しているフランス人の姿もよく見かけるし、英語ができない人の割合が日本と同じぐらい高いというフランスの状況も変わりつつあることを感じる。語学学校の先生たちもたいていみんなペラペラで、前に通っていたパリカト(パリ・カトリック学院)では、英語を話せることが教師として採用されるために必須だったんじゃないかと思う。確かに、まったくフランス語ができない状態で来た生徒たちにとっては、英語が大きな助けになるだろうし。
典型的日本人である私は、もちろん英語なんて話せない。とはいえ最低限の会話はできるし、これだけフランス語にどっぷり浸かっていてもまだ英語のレベルの方が高いと思う。義務教育と大学受験の効果というのはなかなか侮れない。あのころ授業で毎日英語に触れていたことを考えると、まだまだフランス語に接している時間は少ないのだ。でも実際に英語を使えるようになったのは、何度も海外に一人でふらふら出かけているうちによく使うフレーズを覚えてしまったことが大きく、あらゆる場面でどうしても英語を話さなければいけない必要に迫られたことで、英語で考えて口に出すことがスムーズになった。そうでなければ、知識だけはやたら豊富だけど簡単な会話もできないという状態にとどまっていたと思う。だからやっぱり、言葉を習うときには使う練習が欠かせない。
でも、実は英語は嫌い。元々は好きで勉強も苦じゃなかったのだけど、旅行で英語を覚えていくのと同時に、“しゃべれて当たり前”という世界の中での英語の位置付け、そして英語を話す人たちの認識が分かってきて、だんだん嫌悪感を持つようになってしまった。特に英語圏の人たちは、外国人がみんな英語を話してくれるという状況に甘えて、他の国の言葉をぜんぜん学ぼうとしないように見えるから、ますます英語を勉強するのが悔しい。もちろん、語学学校にはフランス語を学んでいるアメリカ人やイギリス人もいるし、すべての人に当てはまるわけはないのだけど、一度持ってしまったその印象はなかなか消すことができない。
それに、英語って単純なのだ。きっと日本語と比べてもそうだろうけど、よく似ているフランス語と比較してみても英語の構造はかなりシンプル。しゃべれないから偉そうなことは言えないとはいえ、英語はやっぱり世界に数ある言語の中でも習得しやすいものなんだと思う。日本人で英語を身につけた人でも、フランス語は難しくて英語のようにはいかないと言っているし、どうせなら複雑なフランス語の方をマスターしたい。
英語が嫌いになった理由には、音の問題もある。これも一般化してはいけないことは承知の上で、イギリス人のカクカクした英語は聞き取りやすいけどあまり好きじゃないし、アメリカ人の流れるようなだらだらした話し方はもっとイヤ。パリでも通りや電車で英語が耳に入ってくることは多いけれど、あのやる気のなさそうな音の連なりが聞こえてくると、舌打ちしたくなるほどイラッとしてしまう。フランス語をここまで勉強してきて思うのは、発音自体は難しいけれど、慣れてしまえば聞き取りはもしかしたら英語より楽かもしれないということ。単語と単語をつなげて読むというルールに惑わされはするものの、一部のアメリカ人が話す英語のように単語の“形”自体がくずれることはない。ただ、ドイツ人が話す英語の音は本当にきれいだし、ああいう英語なら話してみたいなという気になる。
語学学校の生徒たちも、国籍にかかわらず英語ができる人が多い。先進国出身でしゃべれないのは本当に日本人ぐらいで、それもまったくできないという人がほとんど。彼らに比べれば私のレベルでもだいぶ上の方なのだけど、それでも“旅の英会話”の範囲を超えた話になるとぜんぜんついていけないし、嫌いと言いながら実は英語ができないことにはかなりのコンプレックスを持っている。実際に今までの旅行でも、英語が話せないことで何度も肩身の狭い思いをしたので、それがトラウマになっている部分もあるかもしれない。だから今の学校のように欧米人ばかりだと、真っ先に英語での会話になることが頭に浮かんで気後れしてしまう。
パリカトに通っていたときも、共通語は暗黙の了解で英語だったし、こちらがしゃべれるかどうか確かめもせずにいきなり英語で話しだす人も多かった。まあ今ぐらいのフランス語のレベルなら英語になってもついていけるのだけど、一度グループワークで誰かが英語を使い始めたとき、ベトナムの女の子が「英語分からないからやめて」とはっきり言ったのには心の中で拍手喝采。それでいいのだ。確かに今の時代、英語ができないことは胸を張れることじゃないかもしれないけれど、全員がしゃべれる必要もない。だって、フランス語を学びに来ているのだから、そもそも英語を使う方が間違っている。
日本では英語教育の開始年齢が低くなってきて、これに関してはいろいろ意見があると思うけれど、個人的には賛成。前は、日本語もあやふやな段階で英語をやってもどうかなと感じていたのだけど、自分が英語やフランス語を勉強してきて、特にフランスへ来て、やっぱり早い方がいいと思うようになった。というのは、英語ができてもできなくても、物事をしっかり考える人は考えるし、考えない人は考えない。結局は言葉の問題じゃないのだ。中身のないことしか言えないのであっても、英語を話すことができれば可能性が広がるので、まだ自然に覚えられる年齢で身につけておいた方が得なんじゃないだろうか。アイデンティティーの問題を指摘する人もいるけれど、日本にいるのだから、英語を学んだところでやっぱり日本人として育つと思うし。まあこの辺は知識がない上に自分に子供もいないので、あまり軽々しくは言えないけれど。
フランスでこんなことを考えるのもなんだけど、それでもやっぱりどこかで英語はきちんとやらなければいけないなと思っている。ただ、フランス語に対するのと同じような情熱はないので、いつ始める気になるかは自分でも疑問。好きだからじゃなく、必要だからやるのだ。それにしても、英会話を習い始める理由として定番の“外国人に道を聞かれたときに困るから”というのはどうかと思う。それぐらいなら答えられるというのもあるけれど、そもそも自分の国にいるのに外国語がしゃべれないから委縮するなんて、日本人て何て奥ゆかしいんだろう。個人的には、英語で聞かれたら堂々と日本語で返してやればいいと思っている。外国ではさらっと英語でスマートに、というのを理想に掲げつつ・・・。
面白いのは、語学学校にいる英語圏の生徒たちが、自分はフランス語を使いたいのに知り合いのフランス人がみんな英語でしゃべるので不満だと話していること。先生たちもそれを聞いて、フランス人も英語を練習したいんだろうねと言っている。ここまで英語がフランスに侵入しているとはちょっと意外。ちなみに、フランス語にも日本語と同じように、英単語を自国の言葉としてそのまま使っているものがたくさんある(まあそれでも、日本語化している英語の方が断然多いと思うけれど)。そもそも似たような言葉がたくさんあるのに加えて、自分たちが普段使っている単語を共有しているなんて、やっぱり英語圏の人たちはフランス語を学ぶ上で圧倒的に有利だ。でも、だからこそやつらには絶対に負けたくない。少なくともフランスにいる語学留学生にとっては、英語よりもフランス語ができることの方が価値が高いはずなのだから。