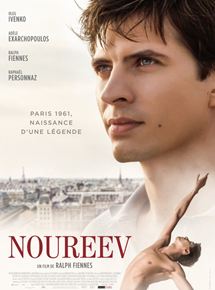フランスは世界に冠たるバカンス大国。有休は年に5週間で、ある調査によれば消化率は100%(ちなみに日本は先進国中、最下位)。年度末でもある夏はフランス人がこぞって休みを取る時期で、8月のパリには観光客しかいないと言われるのは象徴的。テレビはゴールデンタイムにドラマの再放送、いつものニュースキャスターも1カ月ぐらい見かけないし、帰ってくるとみんなそろっていい色に焼けているのには苦笑いを通り越して感心してしまう。フランス語でバカンスは「des vacances」と常に複数形で、「vacancier=休暇を楽しむ人」という単語もある。
その長い休みをどこでどうやって過ごすかというと、旅行でもなく、家でごろごろでもなく、南仏の海辺や緑にあふれた田舎でのんびりするのが定番なんだそう。夏だけ使う別荘を持っている家庭もけっこうあるらしく、期間が長ければ長いほどその別荘で何もしないゆっくりとした時間を楽しみ、余った休みで外国を旅行すると話してくれたフランス人もいた。確かにフランス映画にはバカンスを描いたものが多いし、夏の太陽をたっぷり浴びながら自然の中で遊びまわる子供たちの姿もよく登場する。
この時期になると毎年、バカンス先として人気の町や村などがニュース番組で紹介されるのだけど、同時に留守中の家の管理、ペットの世話など、きっとバカンスに出かける人たちにとっては“頭の痛い”問題であろう話題も取り上げられる。長ければ1カ月間、地域一帯どころか国中の家庭が一斉に家を空けるという日本ではありえない状況の中、実際に空き巣も増えているらしく、ペットを預かる業者やアルバイトも需要が多いとのこと。
このバカンス文化の徹底ぶりは、8月のパリを歩けばすぐに感じることができる。お店が文字通り、軒並み閉まっているのだ。本屋やパン屋、不動産屋といった、特に夏という季節が重要でない店はもちろん、サマータイムで遅い時間までテラス席がにぎわうはずのカフェも、まさに書き入れ時であるはずのアイスクリーム屋も、観光客の期待を裏切って遠慮なく休む。といっても全部の店が閉まるわけじゃなく、観光地のレストランやみやげ物屋はやっているけれど、そこを外れて住宅街に近い通りをちょっと歩けば、各店の入り口にバラエティー豊かな夏休みのお知らせを見つけることができる。短くても2週間は休業するのが一般的なよう。
また、閉めている間に工事をする店も多く、こういう光景もフランスの夏の風物詩。
一方、パリではこの季節、セーヌ川沿いに「パリ・プラージュ」が現れる。プラージュは海辺という意味で、要するにセーヌ川を海に見立ててパラソルで夏らしさを演出し、海岸にいる気分を味わおうということらしい。日本にいるときからこの企画は知っていて、そんなに海が恋しいのかと半分あきれていたのだけど、つい先日まで一度も実際に見たことがなかった。この日はあいにくの曇り空で肌寒かったのだけど、暑い日には水着でくつろぐ人もいるみたいだから、いろいろな事情でバカンスに出かけることができないパリっ子もここで夏を満喫できるのかも。
20代のころ、フランスでは2週間未満の休みは休みではないというような日本の新聞のコラムを読んで衝撃を受けた覚えがある。フランスがバカンスの国だというのはよく知られているけれど、本当にこんな感じで社会の動きが止まるのだ。最初、まさかスーパーまで閉まるのかと不安だったのだけどさすがにそんなことはなく、日常生活には支障なし。ありがたいことに、ほとんどの映画館もちゃんと開いているし。不便と言えば、毎週発行のパリのイベント冊子が、近所のキオスクが一斉に閉まってしまったため手に入らないことぐらい。
日本にいたときは、休みが取れるかどうかは働き方の問題だと思っていたし、実際“働き方改革”なんて言われているけれど、働き方は、つまり生き方だ。最近ではだいぶ世間の意識が変わってきたとはいえ、日本ではまさにこの時期のお盆や、お正月、ゴールデンウィークでさえまだまだ1週間以上の休みを取ることは難しく、たったの3日でも有休を続けて取るなんて夢のような話。たとえ仕事はどうにかなったとしても、周囲の雰囲気がそれを許さない。
毎日残業して年に1度の海外旅行さえかなわず、仕事(会社)にすべての時間を捧げる人生と、平日もプライベートを大切にし、さらに毎年必ずある長い休暇でたっぷりリフレッシュできる人生。価値観は様々だとはいえ、どちらが人間らしく、充実しているかは考えなくても分かる。好きなことをする時間もないなら、何のために生きているのか分からない。老後だけを楽しみに何もかも犠牲にして働くなんて、やっぱりおかしいのだ。人生は自分のためにあるのだから。
曜日や季節に関係なくいつでもほしいものが手に入り、必要なサービスを受けられる日本は、利用する側にとっては便利な一方で、働く側は休めないというジレンマを常に抱えている。日曜にスーパーが閉まることさえ不便に感じてしまうけれど、それが普通になればそのうち気にならなくなる。休むことが前提で、その間は仕事がストップしても仕方ないという意識を社会全体で共有できなければ、個人単位でいくら頑張ったところで上司の命令には逆らえないし、クライアントの要求は断れない。結局は考え方を変えることが一番の近道なのだけど、同時に一番難しいことでもある。まあそのうち日本でも年に3日ぐらいは(強制以外の)有休を取れるようになるかも……っていうのは、楽観的すぎる?
これを書いている途中、まさに同じテーマの面白い記事を発見:
長い夏休み中「フランス」社会はこう回っている(東洋経済オンライン)